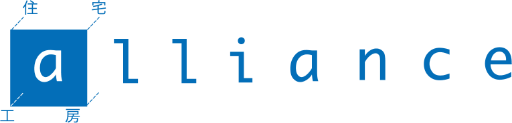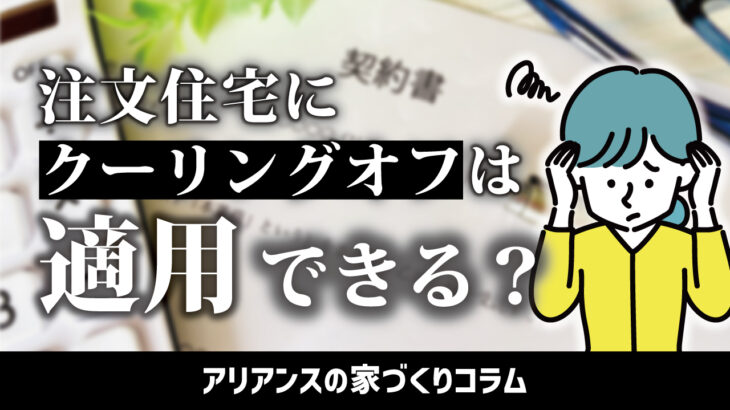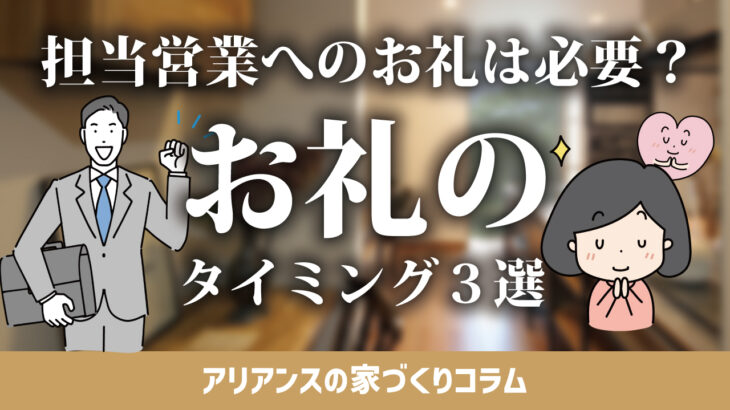- コラム
2025.09.01
注文住宅は契約後でもキャンセルできる?流れと注意点を徹底解説
注文住宅は、理想の住まいをゼロから形にできる魅力があります。しかし、実際に契約をした後に「やっぱりやめたい」「別の会社に依頼したい」と考える人も少なくありません。とはいえ、契約後のキャンセルにはリスクが伴います。違約金が発生する可能性や、トラブルに発展するケースもあるため、正しい知識を持って判断することが大切です。
本記事では、「注文住宅 契約後 キャンセル」というテーマで、契約後にキャンセルできるのか、その方法や注意点、実際の事例まで詳しく解説していきます。
注文住宅は契約後でもキャンセルできるのか?
まず結論からいうと、注文住宅の契約後でもキャンセルは可能です。しかし、その条件や発生する費用は契約内容やキャンセルのタイミングによって大きく変わります。
一般的には以下のような段階に分けられます。
- 仮契約段階
仮契約金(申込金)を支払っているケースが多いです。仮契約の段階であれば、比較的キャンセルはしやすく、支払った申込金も一部または全額返金されることがあります。ただし、返金不可としている会社もあるため契約書を要確認です。 - 本契約前(工事請負契約前)
設計契約や詳細打ち合わせを進めている段階では、実費(設計料や調査費用)が発生する場合があります。 - 本契約後(工事請負契約後)
工事請負契約を結んでからのキャンセルは原則として「違約金」が発生します。金額は契約内容に明記されていることが多く、工事進行状況に応じて数十万円から数百万円になることもあります。
契約後のキャンセルにかかる費用と違約金
注文住宅の契約をキャンセルする場合、最も気になるのが「いくら費用がかかるのか」という点でしょう。
一般的な違約金の目安は以下の通りです。
- 設計段階でのキャンセル:設計費用、測量費用など実費分(数万円〜数十万円)
- 着工前のキャンセル:請負代金の5〜10%程度が違約金として設定されることが多い
- 着工後のキャンセル:実際の工事進捗に応じて支払い義務が発生(数百万円規模になることもある)
契約書には「契約解除に関する条項」が必ず記載されています。そこに明記された違約金や精算方法を確認し、内容を理解することが不可欠です。
契約後にキャンセルしたい理由とは?
なぜ多くの人がキャンセルを考えるのでしょうか。代表的な理由は以下の通りです。
予算オーバー
注文住宅では、初期段階で提示された概算見積もりと、最終的な契約金額に差が出ることがよくあります。特に以下のような要因で、当初の予算よりも大幅に増額してしまうケースがあります。
- オプションの追加:システムキッチンやバスルーム、床材や照明など、標準仕様からグレードアップするたびに費用が膨らみます。
- 土地条件による追加費用:地盤改良工事や造成工事が必要になる場合、数十万〜数百万円の追加費用がかかることがあります。
- 外構や諸経費の見落とし:建物本体の費用だけでなく、外構工事や登記費用、火災保険料なども必要です。
その結果、ローン審査に通らなかったり、返済計画が厳しくなったりして、キャンセルを考える人が出てきます。「この金額であれば無理なく支払える」というラインを明確にしておくことが、契約前の重要な準備です。
住宅会社への不信感
住宅会社との信頼関係が崩れると、契約後であっても「このまま任せていいのだろうか」と不安が強まり、キャンセルを考えるきっかけになります。
- 説明不足:費用の根拠や工事の進め方が不透明で、質問してもはぐらかされる。
- 担当者との相性:レスポンスが遅い、要望を軽視するなど、対応に不満を感じる。
- 会社の評判:ネットや口コミで施工不良やアフターサービスの悪さが目立つ。
こうした小さな不安が積み重なると、「もっと誠実に対応してくれる会社に任せたい」と考え直すのは自然なことです。ただし、不信感を理由にしても違約金が免除されることはほぼありません。そのため、契約前に会社の評判や担当者との相性をしっかり見極めることが不可欠です。
ライフスタイルの変化
契約から引き渡しまでには、少なくとも半年〜1年程度の時間がかかります。その間にライフスタイルが大きく変わる可能性もあります。
- 転勤の辞令:勤務先の異動で他県に引っ越す必要が出た。
- 家族構成の変化:妊娠や親との同居などで、当初のプランでは合わなくなる。
- 収入の減少:リストラや収入減により、ローンの返済が厳しくなる。
これらは「不可抗力」といえる理由ですが、契約解除にあたってはやはり違約金や実費が発生します。住宅は人生計画と密接に関わるため、契約前に“もしも”のシナリオを考えておくことがリスク回避につながります。
急な事情
病気や親族の介護など、突発的な事情で建築を断念せざるを得ないこともあります。
- 自身や家族の病気:治療費がかさみ、住宅ローンどころではなくなった。
- 親族の事情:親の介護のため実家に戻らざるを得なくなった。
- 家庭環境の変化:離婚や家庭内トラブルで住宅計画そのものが破綻した。
こうしたケースは感情的にも大変つらい状況ですが、契約自体は法的効力を持つため、情状酌量でキャンセル料が免除されることはほとんどありません。早めに会社に状況を伝え、誠意を持って交渉することが大切です。
こうした理由は誰にでも起こり得ます。しかし、「やむを得ない理由」であっても、違約金が免除されるわけではありません。
キャンセルを検討する際の手順
契約後にキャンセルを考えた場合、感情的に動くのではなく、以下の手順を踏むことをおすすめします。
- 契約書を確認する
まずは工事請負契約書や重要事項説明書を読み直しましょう。キャンセルに関する条項が必ず記載されています。 - 住宅会社に相談する
直接「キャンセルしたい」と言うのではなく、「契約解除の規定について確認したい」という形で問い合わせるとスムーズです。 - 専門家に相談する
不安があれば弁護士や住宅専門の相談窓口に相談しましょう。消費生活センターでも相談可能です。 - 交渉する
場合によっては違約金の減額や支払い方法の調整ができることもあります。
実際にあったキャンセル事例
注文住宅の契約後にキャンセルを検討する人は少なくありませんが、実際にどのようなケースで発生し、どの程度の費用や影響があったのかは気になるところです。
ここでは、実際に起こったキャンセル事例を紹介します。具体的なケースを知ることで、自分が同じ立場になったときの判断材料になり、契約前に注意すべきポイントも見えてくるはずです。
事例1:設計段階での解約
あるご家庭は、設計契約を結んだ後に他社の提案を受け、「こちらのプランの方が魅力的」と感じて乗り換えました。その結果、既に支払っていた設計料20万円は返金されませんでした。
ポイント:設計契約は比較的軽い段階ですが、それでも設計士が時間を割いて図面を作成しているため、費用が無駄になるリスクがあります。「設計段階=まだ自由にやめられる」と思い込むのは危険です。
事例2:請負契約後のキャンセル
本契約(工事請負契約)を結んだ後、勤務先から急な転勤辞令が出たケースです。結局その土地で建てることができなくなり、契約を解除。結果として請負代金の5%にあたる150万円を違約金として支払うことになりました。
ポイント:契約後すぐのキャンセルでも、違約金は発生します。特に「請負契約」は住宅ローン契約の前提になるほど重い契約であり、キャンセル=大きな出費と考えておくべきです。
事例3:着工後のキャンセル
別の事例では、着工後に住宅ローンの本審査が通らないことが判明。工事は既に進んでおり、会社からは実費精算として約500万円の請求を受けました。
ポイント:ローン審査は「仮審査OK=本審査も通る」とは限りません。特に着工後のキャンセルは損失額が非常に大きくなります。ローン審査は工事契約前に必ず本審査を済ませることが重要です。
トラブルを避けるためのポイント
契約後のキャンセルで最も避けたいのが「トラブル」です。そのために気を付けたいことは以下です。
契約前に「解約条項」を必ず確認する
工事請負契約書には必ず「解除に関する条項」があります。そこには「いつまでならキャンセル可能か」「違約金はいくらか」が明記されているため、ここを事前にチェックすることが重要です。
曖昧な説明しかされない場合は書面で確認する
「大丈夫ですよ」「その時は考えましょう」といった曖昧な返答は危険です。口約束では後から主張が食い違い、トラブルになります。必ず書面で確認し、署名・押印された資料を残すことが安心につながります。
仮契約・申込金の返金ルールを明確にする
「申込金は全額返金」「一部のみ返金」「返金不可」など、会社によってルールが異なります。支払いの前に必ず確認しましょう。返金不可であれば、無駄に支払うリスクを減らすため、最小限の金額にしておく交渉も可能です。
契約直後であっても、気になる点があれば早めに相談する
「もう契約してしまったから…」と不安を放置すると、着工が始まり取り返しがつかなくなります。契約直後であれば交渉の余地があるケースも多いため、気になる点はなるべく早く相談して解決することが、後の大きな損失を防ぐポイントです。
契約前にできるリスク回避策4選
「キャンセルしなければよかった」と後悔しないために、契約前にできる対策も重要です。
ここでは4つのリスク回避策を提示させていただきました。
複数社で相見積もりをとる
注文住宅を検討するとき、最初に出された一社の見積もりだけで契約してしまうと、価格やサービス内容が適正なのか判断できません。複数社から相見積もりを取ることで、費用の相場や提案内容の違いを比較できるため、より納得度の高い判断が可能になります。
例えば、A社では本体工事価格が安く見えても、オプション費用が高額に設定されている場合があります。一方、B社では最初からある程度標準仕様が充実していて、追加費用が少なく済むこともあります。こうした違いは、一社だけでは見えてきません。
さらに、見積もりを比較することで「この金額は妥当なのか」「オプションでどこまで上げられるのか」といった交渉材料にもなります。最低でも3社程度から見積もりを取り、条件を比較して検討することが安心への第一歩です。
契約内容や条項を専門家に確認してもらう
工事請負契約書や設計契約書には、多くの専門用語や法律的な表現が並びます。一般の人にとっては理解が難しく、「大丈夫だろう」とそのまま署名してしまうケースが少なくありません。しかし後からキャンセルやトラブルが起きた際に、この「解約条項」「瑕疵担保責任」「遅延損害金」などの条文が大きく影響します。
不安がある場合は、弁護士やファイナンシャルプランナー、不動産に詳しい専門家にチェックしてもらうのがおすすめです。費用は数万円かかる場合もありますが、数百万円の違約金やトラブルを防げると考えれば安い投資といえるでしょう。
予算に余裕を持って計画する
住宅ローンの返済計画を立てる際、年収から「借りられる金額」をベースにしてしまいがちですが、実際には「無理なく返せる金額」で計画することが大切です。
たとえば年収500万円の家庭であれば、金融機関からは3,500万円〜4,000万円程度の借入が可能とされます。しかし、毎月の返済額が10万円を超えると、教育費や生活費の負担が大きくなり、将来的に支払いが苦しくなる可能性があります。
また、建物以外にも外構工事や引っ越し費用、家具・家電の購入、固定資産税などさまざまな出費が発生します。建築費用だけでなく、周辺の諸費用も含めて「トータルの予算」を考え、少なくとも数百万円程度の余裕資金を持って計画することが理想です。
仮契約・申込金の金額や返金可否を事前に確認する
注文住宅を検討していると、多くの会社で「仮契約」や「申込金」の支払いを求められることがあります。これは住宅会社としても真剣にプランを作成するための証拠金のようなものですが、その金額や返金ルールは会社ごとに異なります。
- 申込金が5万円で、全額返金されるケース
- 申込金が10万円で、一部のみ返金されるケース
- 申込金が20万円で、キャンセル時は返金されないケース
このように幅があるため、支払う前に「返金されるのか」「どのタイミングまでなら返金可能か」を必ず確認し、書面に残してもらうことが重要です。
仮契約段階で「返金不可」となっている場合は、申込金の金額をできるだけ低く交渉することも可能です。無駄なリスクを減らすために、納得できる条件で仮契約に進むようにしましょう。
まとめ|注文住宅の契約後キャンセルは慎重に
注文住宅は人生で最も大きな買い物の一つです。契約後にキャンセルすることは可能ですが、タイミングによっては数百万円単位の費用が発生するリスクがあります。
だからこそ、契約する前にしっかりと内容を確認し、不安があれば必ず相談してから署名することが大切です。
もしどうしてもキャンセルせざるを得ない場合は、冷静に契約書を確認し、必要に応じて専門家に相談しながら進めましょう。
契約は「家づくりのスタート」であると同時に「大きな責任」を伴う行為です。慎重に判断し、納得のいく住まいづくりを進めてください。