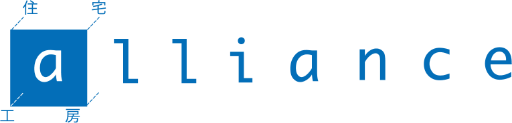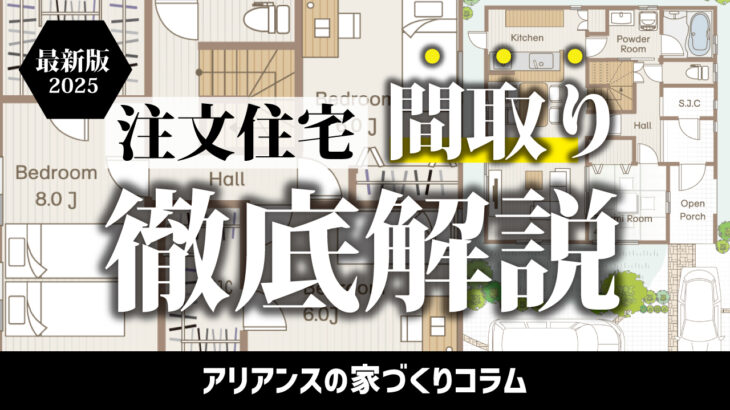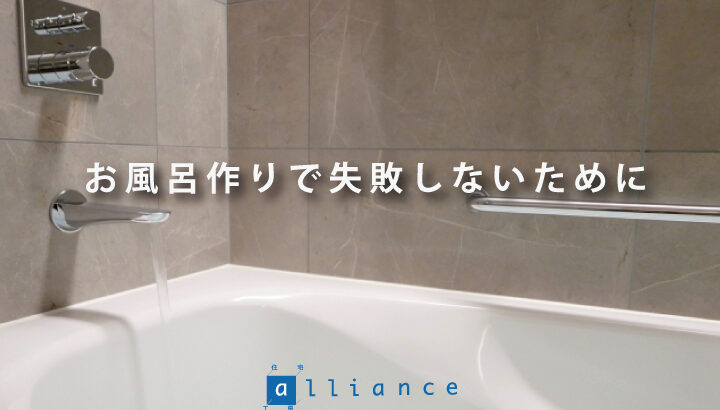- コラム
2022.12.27
知らなきゃ損!失敗することの多い窓の配置を考える時のコツ7選を公開!
通風や採光などの機能性を左右する窓の配置。
これだけでも十分に難しいのに、機能性だけに着目しすぎれば、外観からのデザインが残念なことになってしまうこともあります。
配置によってはお隣の方とやたら目が合うような、プライバシー性の欠けた家になってしまう可能性も否定できません。
窓の配置で失敗しないためには、機能性とデザイン性の両立を実現することが大切です。
今回は、窓の配置を考える時のコツをご紹介します。
お悩みの方はぜひ参考にしてくださいね。
窓の種類
まずは新築で使われることの多い窓の種類について確認していきましょう。
それぞれの種類によって、通風性や採光性・デザイン性は変わってきます。
新築の間取りのイメージやライフスタイルと合わせながら、具体的にイメージしてご覧ください。
引き違い窓

日本で最もよく使われる、サッシを左右に移動させて開閉できる窓です。
地面にサッシがある掃き出し窓にすれば、バルコニーの出入り口にできます。
大きな引き違い窓は開放感を演出できますが、夏の日差しや冬の寒さには注意が必要です。
上げ下げ窓

2枚のガラスを上下に動かして開閉する窓で、欧米の住宅ではよく見かけます。
引き違い窓を縦にしただけのバージョンではありますが、可愛らしい印象が特徴です。
引き違い窓よりも、気密性と防音性が高くなるという嬉しいメリットもあります。
滑り出し窓

回転式に開閉する窓で、通風性が高いのが特徴です。
雨が降ると窓ガラス自体が濡れてしまうデメリットがありますが、スタイリッシュな縦窓が人気を集めています。
FIX窓

FIX窓は窓でありながらも開閉ができず、別名「はめ殺し窓」とも呼ばれます。
防犯性が高いため、大きな窓にしても安心です。
アーチやサークルなど特殊な形状も選べて、ワンランク上のおしゃれさを実現できます。
出窓

壁から飛び出したような形の出窓は、ちょっとした小物置きに活用できるスペースが作れます。
デザイン次第でスタイリッシュにも、可愛らしい印象にも仕上がる点が特徴的です。
ただ、コストが高くなりやすいので注意しましょう。
天窓

屋根面に設置するタイプの窓で、採光性に非常に優れています。
日当たりが悪くなりやすい北側でも、安定して採光を確保できる点がメリットです。
しかし、メンテナンスに手がかかるので慎重に検討する必要があります。
文住宅における窓の後悔は意外と多い
注文住宅を建てた人の後悔ポイントとして意外に多いのが「窓」に関するものです。窓は採光・通風・デザイン性に大きく関わり、日々の快適さを左右します。しかし図面だけで判断すると、実際に住んだときに「思っていたのと違う」と感じやすい部分でもあります。ここでは、注文住宅でよくある窓の後悔とその対策を整理します。
採光不足で部屋が暗い
「南向きだから大丈夫」と思っていたのに、隣家や建物の影で光が入らず日中でも照明が必要になるケースがあります。採光は土地の環境に左右されるため、周辺建物の高さや方角、季節ごとの太陽の動きを考慮することが重要です。吹き抜けや高窓を取り入れて、上から光を取り込む工夫も有効です。
窓が多すぎて家具の配置に困る
採光を重視して窓をたくさん設置すると、結果的に家具を置ける壁がなくなり、生活動線が制限されるという後悔もあります。特に大きな掃き出し窓ばかりだと、収納棚やテレビを配置できずに不便を感じやすいです。窓の数・大きさと家具の配置計画をセットで検討することが大切です。
防犯・プライバシーの問題
通りに面した大きな窓は開放感がある一方で、外からの視線や防犯面の不安を招くこともあります。夜になると室内が丸見えになってしまうケースも少なくありません。すりガラス・縦長窓・ルーバー・外構の目隠しなどを組み合わせて、プライバシーと採光の両立を図りましょう。
断熱性や結露の問題
窓は住宅の中で最も熱が出入りする部分です。断熱性能を軽視すると、夏は暑く冬は寒い家になり、冷暖房費が高くつきます。また結露が発生するとカビや劣化の原因にもなります。ペアガラス・樹脂サッシ・Low-Eガラスなど、性能を重視した窓を選ぶことが後悔防止につながります。
これで失敗なし!窓の配置のコツ7選
窓の種類について把握できたところで、いよいよ窓の配置を考えていきます。
これからご紹介するコツをしっかり押さえることで、ワンランク上の機能性とデザイン性を確保した家づくりができるはずです。
ここでは、窓の配置のコツを7つご紹介します。
1.隣家の窓の配置を確認しておく
隣家の窓と同じ位置に配置してしまうと、あちこち丸見えになってお互いのプライバシーを守れなくなってしまいます。
本人は良くても相手にとっては迷惑なこともあり、近所トラブルのもとにもなりかねません。
隣家の窓の近くには配置しないよう、細心の注意を払いましょう。
2.視線の集まる部分に窓を配置する
廊下や階段、リビングなど、自然と視線の集まりやすい場所には窓を配置するのがおすすめです。
視線の集まる場所に窓があれば、外の眺めを楽しみやすくなります。
もちろんプライバシー性についてはしっかり考えておくようにしてください。
3.窓を配置するということは壁がなくなるということ
文字通り、窓があるということは壁がないということです。
壁がなければ家全体の強度は落ちますし、家具の置き場所も少なくなってしまいます。
窓と壁の配置は連動していることを念頭に入れておきましょう。
4.室内窓を検討する
窓は、外と内を繋げるだけではありません。
室内窓は内と内に繋がりを出し、狭めの部屋でも開放感を演出することが叶います。
光の届きにくいような場所でも、壁ではなく室内窓を配置すれば採光を確保できるでしょう。
機能性もデザイン性もぐっと上がるに違いありません。
5.外から明かりが見えるように配置する
防犯性を考えると、道路側に窓は配置しないほうが良いように感じますが、必ずしもそうとは限りません。
例えば夜の場面では、ある程度外側から明かりが確認できた方が防犯性につながります。
1つくらいは道路側に窓を設置するのがおすすめです。
心配であれば、窓の種類をFIX窓にしたり、小さめの窓にしたりすれば問題ありません。
大きすぎると外から丸見えになってしまう可能性があるので、バランスを考慮しましょう。
6.眺めは窓の配置でコントロールできる
周囲の環境によっては、眺めが良くない場所もあります。
そのような場所では、窓の配置によって眺めをコントロールしましょう。
上の方に見たくない物があるのならば、低い位置を窓で切り取れば良いですし、横の方に見たくない物があるのならば、部屋の逆に窓を配置すれば良いですよね。
見たい風景だけ窓で切り取れるように、配置を考えてみましょう。
ここには窓を配置して!家の中で暗くなりがちな場所とは?
ここまで様々な窓の配置のコツについてご紹介してきましたが、結局は多角的な観点からバランスを考えることが大切であるということです。
明確に窓の配置について指定するとしたら、暗くなりがちな場所に窓を配置することが挙げられるでしょう。
例えば、以下の3点の場所は特に暗くなりやすい場所のため、窓を配置することをおすすめします。
・玄関
・キッチン
・廊下やホール
玄関の窓の必要性については意見が割れやすい場所ですが、採光や通気を考えると配置しておいた方が良いといえます。
玄関は来客の第一印象を左右する場所でもあるので、柔らかな光が差し込む玄関を窓の配置で実現してみましょう。
まとめ
窓は、配置によって暮らしに大きな影響を与えます。
窓の配置において、通風や採光・プライバシー・デザイン性など様々な観点からのバランスを考えることが大切です。
当社では、自然との繋がりを感じやすい窓の配置を実現した家づくりについて提案しております。
ご興味のある方はぜひお問合せください。