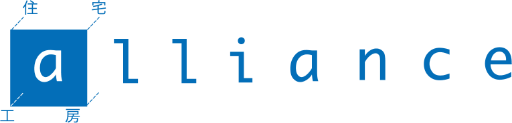- コラム
2025.08.01
注文住宅はクレームが多い?クレーマー扱いされない上手な関わり方とは
注文住宅は、施主の理想を形にする自由度の高い住まいづくりですが、その一方で「言った・言わない」「仕上がりが想像と違う」「対応が悪い」といったトラブルやクレームも少なくありません。
実際に家づくりが進む中で、工務店やハウスメーカーとの認識のズレが発生し、施主側が「クレーマー扱いされてしまう」といったケースも存在します。
本記事では、注文住宅におけるクレームの代表例や、クレーマーと見なされないための正しい伝え方、事前に防ぐための準備と心構えについて詳しく解説します。
なぜ注文住宅でクレームが多くなるのか?
注文住宅では、自分好みの家を一からつくる自由度の高さがある一方で、施主と施工会社の間で「伝えたつもり」「理解したつもり」といった認識のズレが生じやすいことが、クレーム発生の根本原因となります。
ここでは、クレームにつながる主な原因を項目ごとに詳しく解説します。
打ち合わせ内容が記録されていない、または伝達が不十分
注文住宅では数ヶ月〜1年以上にわたる打ち合わせが繰り返されるため、「以前話した内容が抜けてしまう」ことがよくあります。
特に、口頭のみで伝えた内容や、手書きのメモで済ませたような仕様は、現場に正確に伝わらないことも多く、「そんな話は聞いていない」「打ち合わせ時と話が違う」といったクレームが発生します。
対応策としては、仕様変更や要望はすべて書面(またはメール)で残し、正式な確認書として両者が認識を共有することが不可欠です。
工事途中での仕様変更による追加費用への不満
工事が進むにつれて「やっぱりここにコンセントを増やしたい」「棚の高さを変えたい」などの要望が出ることは珍しくありません。
しかし、それに伴う変更工事には当然追加費用が発生することが多く、「ちょっとの変更のはずなのに、なぜこんなに高いのか」と納得できずクレームになるケースがあります。
多くの場合、変更によって職人の手配や資材発注が再調整されるため、想像以上のコストがかかるのです。
施主側としては、「いつまでなら無料で変更可能か」「どの変更にいくらかかるか」を事前に確認しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
引き渡し時の仕上がりに対する不満や発見
家が完成して引き渡しを迎えると、細かい部分が目に入るようになり、「壁紙が浮いている」「床に傷がある」「クロスが剥がれかけている」といった施工不備が見つかることがあります。
施主としては「新築なのにこんな状態で渡すなんて」とショックを受けることもあり、強いクレームに発展することもあります。
こうした仕上がりに関する不満を避けるには、引き渡し前に行う「施主検査」を入念に実施し、不具合をチェックリストに記入して補修を依頼することが重要です。
また、「完璧な仕上がりが当然」という意識ではなく、「人の手でつくられるものだから多少の修正はあり得る」という心構えも、冷静な対応につながります。
担当者の対応スピードや態度に対する不信感
注文住宅の過程では、担当者とのやり取りが密になるため、コミュニケーションの質が信頼関係に直結します。
そのため、以下のような対応は大きな不満につながりやすくなります。
- ・連絡しても返信が遅い、または返ってこない
- ・質問に対して曖昧な返答しかしない
- ・明らかに担当者が現場を把握していない
- ・指摘しても言い訳や責任転嫁ばかりで誠意が感じられない
このような対応が続くと、「もう信用できない」「話が通じない」といった感情的なクレームに発展することもあります。
担当者に対する不満は、対応の質だけでなく、“信頼できる人かどうか”という根本的な印象で判断される傾向があるため、早めに相談窓口や上司に報告して対応を変えてもらうことも検討すべきです。
よくある注文住宅のクレーム例とは?
注文住宅で実際に多く報告されているクレーム事例を知っておくことで、未然に防ぐ手がかりを得ることができます。
【クレーム例1】フローリングや建具に傷がある
床材や扉などの建具に目立つキズが見つかると、施主の不満は一気に高まります。「新築なのにどうしてこんな傷があるのか」と怒りを覚えるのも当然です。
ただし、建築現場は常に多くの職人が出入りし、資材や工具が搬入されるため、細かい傷や擦れが完全にゼロというわけにはいきません。
問題は、「傷があること」ではなく、「そのまま引き渡そうとしたこと」や「説明がなかったこと」にあります。
検査の際に丁寧な補修対応や説明があれば、クレームにならずに済んだという事例も多くあります。
【クレーム例2】ドアや引き戸の建付けが悪く、開閉しにくい
「引き戸が最後まで閉まらない」「ドアが途中で引っかかる」といった建具の建付け不良も、引き渡し時によく見られるクレームの一つです。
これは、地盤沈下や湿気による木材の伸縮、枠の取り付け精度のズレなどが原因となる場合があり、必ずしも手抜き工事とは限りません。
しかし、使いにくさが明らかに感じられる場合には、引き渡し前にきちんと調整してもらうよう依頼することが大切です。
また、数ヶ月後に不具合が生じた場合でも、アフターサービスの対象であれば無償で対応してもらえることが多いため、保証内容を確認しておきましょう。
【クレーム例3】コンセントやスイッチの位置が不便
「冷蔵庫を置こうと思った場所にコンセントがない」「スイッチがドアの後ろに隠れて使いにくい」など、住み始めてから気づく不便さに対するクレームも多発しています。
これは設計段階で「図面上では問題なかったが、実生活で使うと不便だった」といった“想定と現実のギャップ”が原因です。
特に電気配線は施工後の変更が難しいため、事前に家具や家電の配置を具体的にイメージしながら、コンセントやスイッチの位置を決めることが大切です。
【クレーム例4】完成後に「思っていたより狭い」と感じる間取り
図面や3Dパースで確認していたはずなのに、「完成してみたら思っていたより部屋が狭い」「天井が低く感じる」といった視覚的な違和感に対する不満もよく見られます。
これは、図面だけでは空間の広さや高さを正確に体感できないことが原因です。6畳と聞いても、使える壁面の長さや天井高、家具のサイズによって体感は大きく変わります。
解決策としては、モデルハウスの見学や、同じ間取りの施工事例を見せてもらうことで、実際の広さを体感することが有効です。また、設計士に「この空間に立ったとき、どんな印象になるか」を具体的に質問するのもおすすめです。
【クレーム例5】担当者の対応に対する不信感
家づくりの過程で、「この人に任せて大丈夫なのか」と不安を抱かせる対応があると、それ自体が大きなクレームにつながることがあります。
たとえば以下のようなケースです。
- 要望を聞いてくれず話を流される
- 約束を守らず、説明もないまま放置される
- 明らかに知識不足なのに、質問に対してごまかす
注文住宅は高額な買い物であると同時に、感情が大きく動くライフイベントです。そのため、施主の不安を軽視したり、無責任な態度を取られると、「一生の家を任せる信頼関係が崩れる」と感じてしまいます。
対応への不満がある場合は、なるべく早い段階で上司や別の担当者への相談を検討し、ストレスを抱え込まないようにしましょう。
以上のように、注文住宅のクレームには「技術的な問題」と「コミュニケーション上の問題」の両方が関係していることが多くあります。
どれも「事前のすり合わせ」や「丁寧な説明」があれば防げるケースが多いため、施主様としても積極的に情報を共有し、確認を怠らないことが大切です。これらはすべて、「伝えたつもり」と「受け取った内容」にズレがあることで起こりがちです。感情的になる前に、事実ベースで冷静に整理することが大切です。
クレームとクレーマーの違いを理解する
「クレーム」と聞くとネガティブな印象を持たれがちですが、本来の意味は「正当な要求や不満の申し立て」です。一方で「クレーマー」と呼ばれるのは、以下のような過剰な言動や不合理な要求を繰り返すケースです。
- ・大声で怒鳴る、暴言を吐く
- ・本来の契約範囲外の要求を繰り返す
- ・金銭的補償を過度に要求する
- ・SNSや口コミで一方的に会社を批判する
つまり、誠実に要望を伝える「クレーム」は何の問題でもありません。感情的に一方的な攻撃をすると「クレーマー」になってしまいます。不満があっても、冷静かつ根拠を持って伝えることで、建設的な対応が受けられやすくなります。
クレーマー扱いされない伝え方のコツ
せっかくの家づくりで、「また文句を言われた」「面倒な施主だと思われていそう」と感じるのは辛いもの。しかし、伝え方を少し工夫するだけで、正当な主張がスムーズに受け入れられることは多くあります。
ポイント1:記録を残す
「言った・言わない」を避けるために、メールやチャットでやり取りを残すようにしましょう。対面での打ち合わせ後も、「本日の内容をまとめました」と送るだけで認識のすり合わせになります。
ポイント2:感情的に言わない
不満を伝えるときこそ、「どうしてそう思ったのか」「何を改善してほしいのか」を冷静に伝えることが大切です。怒りをぶつけるのではなく、事実と要望を分けて整理することがポイントです。
ポイント3:協力的な姿勢を示す
「一緒により良いものを作りたい」という姿勢は、施工側の印象も良くなります。「こうしたいのですが、可能ですか?」と相談ベースで提案するだけで、対応が丁寧になることも少なくありません。
施主様側が気をつけたいトラブル回避の工夫
クレームを未然に防ぐためには、「相手任せにしない姿勢」も大切です。以下のような工夫を実践することで、不要な誤解やトラブルを避けられます。
- ・図面や仕様書は細かく確認する(記号の意味や寸法も見逃さない)
- ・第三者視点で完成イメージをチェックする(設計士ではなく、他の家族にも見てもらう)
- ・疑問があればその場で質問する(「後で聞こう」は忘れがち)
- ・打ち合わせ内容はメモやメールで残す
- ・完成後のチェックは引き渡し前に入念に行う
注文住宅は施主と施工側がチームとなって進めるプロジェクトです。「言わなくてもわかるだろう」という考えは危険で、言葉にして確認し合う姿勢がトラブル回避につながります。
施工会社の対応力でクレーム対応は大きく変わる
実際、同じような不具合やトラブルがあっても、「丁寧な説明と迅速な対応」があれば、多くの施主様は納得してくれます。その意味で、どの会社を選ぶか(=対応力のある担当者に出会えるか)は極めて重要なポイントです。
信頼できる会社の特徴
- ・契約前から丁寧に説明をしてくれる
- ・トラブル時にも誠実に向き合う姿勢がある
- ・担当者がコロコロ変わらない
- ・「無理なものは無理」とはっきり言ってくれる
- ・過去の施主の口コミで評価が高い
家づくりでは、「技術力」だけでなく「人間力」も大切な選定基準です。トラブルが起きたときこそ、会社や担当者の本質が問われる瞬間です。
まとめ|不満を伝えるのは悪ではない。
注文住宅において、クレームが発生するのは特別なことではありません。むしろ、理想を追求するからこそ、こだわりや要望が増え、すれ違いが起きるのは当然ともいえます。大切なのは、不満を我慢するのではなく、適切な形で伝えること。そして、伝えることで家づくりがより良い方向に進むということを、施工側と施主が共有できることが理想です。
「クレーマーにならないか不安」と感じる方こそ、この記事で紹介したポイントを押さえ、前向きで建設的な家づくりのパートナーシップを築いていきましょう。